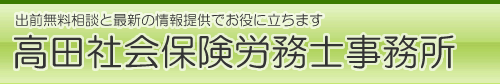作成日:2025/09/18
橿考研
奈良県立橿原考古学研究所(橿考研=かしこうけん)友史会の創立70周年記
念講演会が9月13日、橿原市内であり、勇んで出掛けてきました。友史会は「
橿考研友の会」のような任意組織。橿考研が正式に発足した4年後の1955年、
75人で立ち上がり、「高松塚古墳」や「藤ノ木古墳」の発掘などを機に徐々に
会員が増え、今では1000人を超えているとのことです。
講演会のテーマは「『国家形成』ローマとヤマト」で、大きく出たな、といっ
た気配。橿考研特別指導研究員の寺沢薫さんが「弥生国家論―王権誕生への道」、
橿考研所長の青柳正規さん(元文化庁長官)が「王政期ローマの社会」をそれ
ぞれ1時間強、スライドを使って分かりやすくお話されました。とくに面白かっ
たのが寺沢さんの講演。以前からの自説の紹介のようでしたが、寺沢さんの著作
の詳しい論旨を知らなかった私は驚きました。
奈良盆地の東南、いま桜井市の一角に「纏向(まきむく)遺跡」という、紀元
3世紀初めに忽然と現れた2キロ四方の大きな遺跡があり、今も精力的に発掘調
査が進められています。寺沢さんはこの纏向に至る、3世紀までの経緯をこんな
ふうに描きます。
部族が群雄割拠していた北部九州では2世紀初め、イト倭国(福岡県糸島市)
が一帯の盟主になった。同時に、キビ(岡山県)やイズモ(島根県)も台頭し、
各勢力が拮抗状態になる。一方、大陸は後漢の末期で、東夷への圧力が強まり、
やがて2世紀末には卑弥呼が列島西半分を束ねる女王として後漢・公孫氏の指
導または強制にて「共立」されることとなった。「イト倭国」から、卑弥呼を擁
する「新生倭国」への大展開で、3世紀初めには、新生の首都として纏向が人
工的に造成されるーー。
講演のプログラムには、寺沢さんの講演のダイジェストが載っており、おし
まい近くには「纏向=新生倭国(邪馬台国)=ヤマト王権の誕生」「卑弥呼は
邪馬台国の女王として纏向にいた」と読める箇所があります。ただ、講演で卑
弥呼の名が出たのは「生年がはっきりしない」と断って2回だけ、邪馬台国に
至っては一言もなかったように思います。満席の受講者500人の中に「邪馬台
国=北部九州説、卑弥呼は九州にいた」と主張する一派が入り込み、その見え
ない論客たちを刺激しないように遠慮したのか、とも思いました。
講演が興味深かったのでいたずらに長くなりましたが、21日(日)には、公
開遺跡めぐり「オオヤマト古墳群を巡る〜纏向遺跡から黒塚古墳へ〜」が現地
集合で開催されます。私はこの遺跡めぐりにも参加し、手応えを覚えたら友史
会の会員になろうかな、とも考えています。せっかく奈良で自宅を兼事務所に
したわけですし。