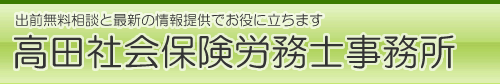作成日:2024/10/16
育介規程
今回は本業にかかわる、ややこしい話。タイトルの「育介規程」は「育児介
護休業等規程」とすることが多い「就業規則」の一種です。であるなら、就業
規則の中に取り込んでもいいのですが、育介規程に入れるべき規定は多く、分
量等の都合で、就業規則とは別建てにするのが普通です。 事業所の育介規程は1992年の施行以来、11回も改定されてきた「育児介護
休業法」にマッチした内容にする必要があります。従業員が法の規定に沿って
育児休業、介護休業をとる場合、そして従業員にこれらを積極的にとらせる企
業を支援する「両立支援助成金」の支給申請を試みる際、常に最新の育介法を
踏まえた個々の育介規程を用意しなければなりません。 この育介規程最新版への独力での改定は正直、面倒です。就業規則や賃金規
程は、労働基準法が求める最低限の基準・規定が守られていれば、および労使
で共有できる分かりやすさがあれば、章立てや条文の順に決まりはないといえ
ます。就業規則特有の大まかな「文法」を意識すれば、表記上の細かな制約も
ありません。 ところが、厚労省・労働局による育介規程の点検は厳格です。実務上は厚労
省のサイトにある「モデル育介規程」をダウンロードし、そのまま会社名を入
れ、最新の育介規程として使うのが無難で安全で妥当といえます(労働局もモ
デル規程のコピーを推奨しています)。 私は育介規程を作って両立支援助成金の支給申請まで持ち込んだのは10回ほ
どで、その都度、育介法の改正を意識し、育介規程を代行で策定してきました。
ただ、その照合・改定作業は煩雑で、最近は上記のようにモデル育介規程を使
うことにしています。というのも、実際上、今やモデル育介規程を使わないと
労働局がウルサイからです。 とはいえ、厚労省のモデル規程をコピーして使うとき、いつも疑問が湧きま
す。妊娠した女性従業員、または父親になることが分かった男性従業員が会社
に赤ちゃんが生まれる旨報告し、会社も、国が推奨する育児休業をとらせたい、
助成金もある、ということで前向きになるとします。 若手(育児休業の取得予備群)が多い中堅以上の法人なら総務や人事が育介
法を勉強して準備を進めるはずですが、そうでない中小・零細の事業所では、
育介法に精通した社労士に依頼するなど、外部に投げた方が速いと思われます。
もっとも社労士側も、育介規程は今や厚労省のモデル規程をコピーして使うの
が近道で、代行する側の裁量の余地はゼロに近い。 しかも、これが最大の難点ですが、モデル育介規程自体、率直にいって、裁
判所の判決の判決理由のような悪文の典型で、二、三回読んでも理解するのに
苦労するシロモノです。 中小・零細の事業所どころか、半年ほど先に(嫁さんの)お産が近づいたシ
ロウトの従業員が、国が勧める育児休業をとろうとしてネットで勉強しても、
あるいは無関心な会社に提案しようとしても、複雑で難解なモデル育介規程の
理解にまで到達するのは至難と思われます。男の育児休業(パパ育休)をとれ
とれ、と勧めながら、それを支える育介法も育介規程も、現場に目を向けてい
ない、たいそう不親切なものではないか、何とかならないか、と私は考えてい
ます。