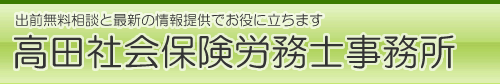作成日:2023/04/18
仇討ち
高野山の京大坂道を歩いてきました。京、大坂からの道が河内長野(大阪府
)で合流して高野山に至る、往時の最短コース。先に歩いた町石道(ちょうい
しみち)と同様の参詣道の一つです。
南海高野線の学文路(かむろ)駅を下車して南下し、割と急な山二つを越え
ます。歩き出して3時間、高野線の終点・極楽橋駅(高野山ケーブルカー駅を
併設)に降り立つ手前の道そばに「黒岩」がありました。元禄赤穂事件を起こ
した浅野家の次の次、赤穂藩を引き継いだ森家家中による「仇討ち」の現場で
す。
現地の説明板や関連資料によると、経緯は次のごとくでした。幕末の1862
年12月、赤穂藩重職で佐幕派の村上天谷ら2人を、勤皇派の下級藩士ら13人
が襲撃して惨殺。政情揺れ動くなか、藩は村上家の廃絶を決め、憤激した遺
児4人は復讐を決意します。一方、藩はその下級藩士らの処遇に困り、やがて
高野山上の森家菩提寺の守役を命じて赤穂から遠ざけようとします。
1871(明治4)年2月、下級藩士らのうち6人が高野山めざして京大坂道
に入りました。情報を掴んだ遺児4人と助太刀3人が先回りして6人を待ち、
出合い頭、遺児らは名乗りを挙げ、槍と刀による激闘の末、6人を殺害し、
10年越しで本懐を遂げた、ということのようでした。
仇討ち組のうち2人が、後ろに潜んで待ち伏せしたという大きな黒岩が152
年前と同様、京大坂道上り手右側にあった次第です。少し下ると討たれた6人
の石造りの墓所が「殉難の士」の表示で残っています。
私が京大坂道を歩いたのは平日で、道中の前後に誰もおらず、天気予報どお
り徐々に曇ってきて肌寒くなってきます。道筋や木立ちの様子は恐らく昔のま
ま。参詣道の一帯が、計13人が斬り合った現場跡だと思うと、気味が悪くなっ
てきました。
「赤穂藩森家中の仇討ち」等を受け、新政権が2年後の明治6年「敵討禁止
令」を出したため、事件は「日本最後の仇討ち」と言われることがあります。
一方、吉村昭さんが短編小説『最後の仇討ち』で描いた、秋月藩(福岡藩支
藩)臼井六郎による亡父の仇討ちは1880(明治13)年で、こちらを「最後」
と呼ぶこともあります。
敵討禁止令は1880年制定の刑法に吸収されて消滅した半面、武家の作法ど
おり自首した村上家、臼井家それぞれの遺児たちは明治の一審法廷で死罪を
宣せられ、上級審で減軽されて10数年で釈放、という扱いで共通したようで
す。
春本番の高野街道を楽しむつもりが、凄惨な殺人事件の現場跡を歩き、禁
止令までは遺族の「壮挙」だった仇討ちのことを考える羽目になりました。
暗く、古臭く、長い話で恐縮です。