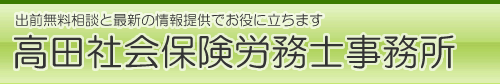作成日:2014/01/09
伏見点描6-高瀬川
 写真は伏見の商店街・大手筋の西を南北に流れる「東高瀬川」です。江戸初期に角倉了以らが開削した物資輸送のための運河で、京都二条から伏見間の約10㌔を結んでいたのが「高瀬川」。琵琶湖疎水への輸送のシフトなどで大正期には役目を終え、東高瀬川は、今も繁華街・木屋町通沿いを流れる本来の高瀬川とは分断された、とのこと。鴨川からの水も入って来ず、流れはゆっくりしています。
写真は伏見の商店街・大手筋の西を南北に流れる「東高瀬川」です。江戸初期に角倉了以らが開削した物資輸送のための運河で、京都二条から伏見間の約10㌔を結んでいたのが「高瀬川」。琵琶湖疎水への輸送のシフトなどで大正期には役目を終え、東高瀬川は、今も繁華街・木屋町通沿いを流れる本来の高瀬川とは分断された、とのこと。鴨川からの水も入って来ず、流れはゆっくりしています。この川は、森鴎外の短編『高瀬舟』でも有名です。行き来していた高瀬舟を舞台とするこの短編があればこそ、高瀬川はそれなりに有名なのでは、とも言えそうです。そこで「伏見点描」をアップするに際し、ブックオフに寄って百円均一の棚から新潮文庫『山椒大夫・高瀬舟』を買い、読んでみました。
わずか16頁の小品で、確か中学生のころに読んで以来。弟殺しの罪人が遠島を申し渡されて護送される、その道中での京都町奉行配下の同心と、まだ年若の罪人との対話を描いています。解説等によると、財産を持つことの意味、および「安楽死」の問題を扱った小説だとのこと。しかし正直なところ、話が淡々とした説明調で、あまりメリハリがありません。『高瀬舟』は実話に基づくらしく、時代小説の名手・藤沢周平あたりが書けば、もっと味のある作品になったのでは、とすら思いました。
しかし、もう少し調べると、『高瀬舟』は発表当時(大正5年=1916年)では斬新だった「安楽死」をテーマにしただけでなく、他にも深い意味がある由。鴎外は、財産の持つことの是非を作中で問うなかで、日本政府が第一次大戦中に発した「対華21カ条要求(大正4年)を暗に批判」している、さらに同心の心中での独り言「妻を好(よ)い身代の商人の家から迎えた」(256頁11行目)とあるのは「日英同盟の寓喩」ではないか、というのです。発表当時に読者に及ぼしたインパクトがそんな「拡大解釈」を生んだのか、和漢洋に通じた文豪だったからこそ「深読み」が広がったのか。このあたり、100年近く前のことなので、実情は不明です。
なお、写真左奥は京セラの本社ビル(高さ95㍍)で、府内で2番目に高い建物。一番高いのは、長岡京市にある日本電産の本社ビル(100.6㍍)。稲盛和夫さんを尊敬する永守重信さんが、尊敬しつつも対抗心を燃やして6㍍ほど高くし、京セラビルが見える最上階に社長室を構えた、という有名な話があります。