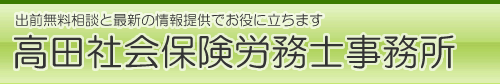作成日:2013/11/19
伏見点描4-電車発祥の地
 左の写真は伏見・大手筋の西の外れ、油掛の交差点にある「我が国における電車鉄道事業発祥の地」の石碑。1895年(明治28年)、七条(現京都駅)―伏見間に軌道が敷かれ、日本で初めて路面電車が営業運転で走った、という伏見側の駅跡地を示します。地味な絵柄で、辺りには駅があった気配もないので、挿入写真は小さくしました。ただ、石碑の左に説明板があり、平日でも少なくない散策中の観光客がのぞき込んだりしています。
左の写真は伏見・大手筋の西の外れ、油掛の交差点にある「我が国における電車鉄道事業発祥の地」の石碑。1895年(明治28年)、七条(現京都駅)―伏見間に軌道が敷かれ、日本で初めて路面電車が営業運転で走った、という伏見側の駅跡地を示します。地味な絵柄で、辺りには駅があった気配もないので、挿入写真は小さくしました。ただ、石碑の左に説明板があり、平日でも少なくない散策中の観光客がのぞき込んだりしています。ものの本によると、日本で初めて電車が走ったのは1890年で、新橋―横浜間における蒸気機関車の鉄道路線開業(1872年)の18年後。場所は東京・上野公園。もっとも、この電車はレールわずか60㍍のイベント用。これに対し、5年後の京都での電車は軌道6.7㌔に及び、琵琶湖疎水の水力で作った電気を配し、客多数を乗せて走ったといいます。伏見に駅ができたのは、淀川を上下する船着き場がそばにあったため。この時の路面電車初代車両は平安神宮に保存されているとのことでした。
京都での路面電車は、後に七条から北に向かって広がり、1918年の全面市営化を経て、軌道が敷きやすかった碁盤目状の市中心部一帯を縦横に結ぶことになります。最盛期は総延長76.8㌔。その後、クルマ社会の進展と交通局事業の赤字累積で、市電は1978年9月末をもって廃止されました。高卒1年後まで宇治に住んでいた私も、濃緑と薄茶のツートンカラーで走る市電には何十回となく乗った記憶があります。頻りに乗っていたのは廃止直前のころ。四条通や河原町通では左右にひしめく車の間を市電がゆっくり動いていたものです。当時はバス以外の車にはめったに乗らない身だったものの、「狭い道を複線で走る市電はいずれ邪魔者扱いされるのでは」と予感していました。
京都の旧市電車両は、よく知られているように、広島電鉄が何両かを譲り受け、他都市の旧路面電車の車両ともども、今も広島市内を走っています。去年、広島に出向いた際、たまたま旧京都市電の車両に乗り当たり、懐かく思ったことを覚えています。