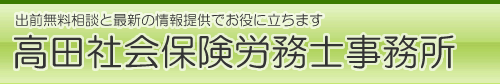作成日:2013/10/19
伏見点描3-酒蔵
 伏見はかつて「伏水」とも書いた名水伏流の地。兵庫県南東部の「灘五郷」と並ぶ酒蔵の集積地です。今日は黄桜酒造が無料公開している「キザクラカッパカンパニー」構内に車をとめ、一帯を散歩。私は清酒の業界事情や流行には疎い方です。それでも、黄桜のほか、かつて清酒最大手だった月桂冠、さらに宝酒造(銘柄は「松竹梅」)、キンシ正宗など、清酒メーカー20数社が登記上の本拠をここに構えていることは聞いています。
伏見はかつて「伏水」とも書いた名水伏流の地。兵庫県南東部の「灘五郷」と並ぶ酒蔵の集積地です。今日は黄桜酒造が無料公開している「キザクラカッパカンパニー」構内に車をとめ、一帯を散歩。私は清酒の業界事情や流行には疎い方です。それでも、黄桜のほか、かつて清酒最大手だった月桂冠、さらに宝酒造(銘柄は「松竹梅」)、キンシ正宗など、清酒メーカー20数社が登記上の本拠をここに構えていることは聞いています。上の写真はCMで河童の漫画を使った黄桜のカッパカンパニーに入る道筋で、右手の建物は黄桜記念館。南に7分ほど歩くと「月桂冠大倉記念館」、他にも酒蔵の街らしい雰囲気を残した家並みが続きます。土曜日で、外国人を含む大勢の見物客が三々五々のんびりと散策していました。
昨年末、京都市議会が議員提案で全国初の「清酒の普及の促進に関する」条例を全会一致で可決(今年1月施行)。その条例が理念・目標としてうたう「清酒で乾杯」の習慣の「周知徹底」を狙ったイベント等のポスターも随所で見掛けました。先日、京商のビジネス交流会で立ち話した伏見の酒販店店主は「あの条例は伏見の酒造組合が『おもろいアイデアやで』と市会議員を突き上げて出来たんや」とまことしやかに。全国で20を超える自治体が後を追って同様の条例を可決・施行したといいますから(当然、鹿児島では「焼酎で乾杯を」条例)、京都発の久々のヒットというところかもしれません。
日経新聞京都支社が編集した新書『京都ここだけの話/第2弾』によると、京都市におけるビール1人当たりの消費額は全国1位とあります。ただ、関連するページをネットで覗いても、消費量は東京が1位云々とあっても、京都の消費額が1位だというデータは見つけられずじまい。けれど、伏見という清酒の産地を抱えながら、ビールを飲む人が多いという印象は以前からありました。全国でみても、1975年に年間で168万㌔㍑だった清酒の消費量は、2011年でざっと3分の1強の60万㌔㍑にまで減っているとのこと。
私も、昔はともかく、今はあまり清酒は飲まない、というより飲めなくなりました。嗜好・体質の変化でしょうか。一方、和食には清酒が最も合う、という清酒好きの言い分は十分に理解できます。酒蔵群を歩いたことで、久しぶりに口あたりのいいお酒を楽しんでみようか、という気になった次第です。